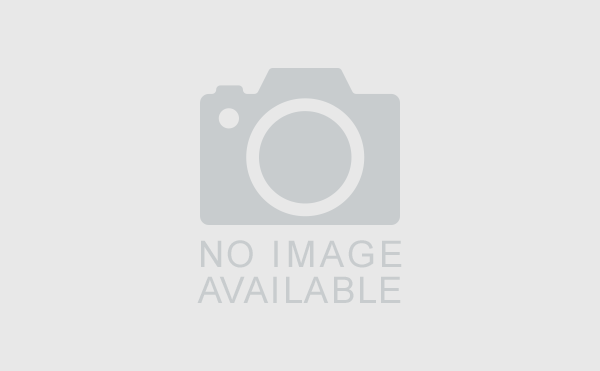令和7年第4回定例会の本会議で代表質問を実施しました!
本日、令和7年第4回定例会の本会議で代表質問の機会をいただき、私から、今回は教育施策に絞った3点について質問をいたしました。
質疑応答の概要を以下のとおりご報告申し上げますので、ご確認いただき、ご意見・ご要望などございましたら是非ともお声をお寄せください!
(★本ホームページの“お問い合わせ”から私に直接メールをご送信いただけます)
【本区で育ちゆくこども達への投資について】
(答弁者:大久保区長)
Q:
日本国憲法第26条では“義務教育は無償”と定められており、我が国では授業料や教科書も無償で給与されている。
また、東京都が国に先立ち、学校給食費の無償化や私立高校の授業料軽減助成金を創設して子育て政策を推進してきているが、23区内の各区でも修学旅行費を無償化したり、学校の教材費まで無償化の枠組みを拡大していく動きがある。
このようなこども達への投資の現状について、本区の認識をうかがう。
A:
義務教育にかかる費用は、本来は国において全国一律で検討するべきであるが、そのような子育て支援は必要なものと考える。
また、本区では従前より、こども医療費無償化を高校生相当まで拡大したり、令和5年度には18歳以下のこどもを養育する世帯へ電子クーポン3万円を配布するなど、取り組みを進めてきた。
Q:
私から昨年11月の本会議代表質問に続き、本年6月の補正予算審査特別委員会においても提言をしたとおり、「小1の壁※」の解消を目的に、区立小学校の朝の開門時間を午前7時30分に前倒しをするトライアルが夏季休暇明けから始まったことは評価をする。
しかし、その担い手は提言をしてきた“きっずクラブ運営事業者”ではなく、シルバー人材センターで実施されている。
現状は懸念を伝えてきたとおり、3校でトライアルを開始する予定が、シルバー人材センターで担い手が確保できず、予定されていた豊洲北小学校では本日現在、未だ開始日が定まっていない。
やはり、日頃から児童と顔の見える関係が構築されている“きっずクラブ運営事業者”を担い手とすることで、人員の確保も含めて安定的に、速やかに区内46校で全校で本格実施を開始するべきと考えるが、見解をうかがう。
A:
シルバー人材センターを担い手として2校でトライアルを開始したが、豊洲北小学校では人員確保ができておらず、本格実施には他の委託先の確保が必要であると認識しており、きっずクラブ運営事業者や地域住民による見守り体制の構築も含めて様々な方策を検討する。
また、利用者からは「是非利用したかった」「大変助かっている」というお声をいただいているが、年度途中にトライアルを開始した影響もあり、日々の利用者が少ないことも課題である。
今後は、利用者の意向などの検証や利用状況の分析を行い、事業を充実するよう検討をする。
(感想)
懸念を伝えてきたとおり、トライアル3校の検証を実施するどころか、未だに1校はトライアルが開始されていない惨憺たる状況です。
江東区教育委員会は、本事業について早期に全校展開を目指す意気込みが無いことが露呈されたので、今後も引き続きあらゆる機会で追及してまいります。
<※小1の壁とは>
小学校の登校時間は保育園の登園時間より遅くなり、生活スタイルも変わるため、多くのご家庭では母親が働き方を変えるか、あるいは退職せざるをえなくなる社会現象。
【教員による盗撮防止に向けた公用スマートフォンの貸与を】
(答弁者:教育委員会事務局次長)
Q:
学校公開の際など、教員の私用スマートフォンが使用されている授業風景を目にすることがあるが、全国各地では盗撮被害が相次いでいる。
また、こども家庭庁からは、教育施設内に防犯カメラの設置が有効である、との案も示されているが、その抑止効果に期待はするものの、犯罪自体を未然に防止しなければ意味がない。
そこで、公用スマートフォンを各校に2台ずつ貸与をして、例えば、授業の音源で使用することを希望する教員へ貸し出すことで教員の授業展開を応援したり、撮影画像のチェックをすることを提案する。
また、公用スマートフォンを貸与することで、教員の私用スマートフォンの職員室からの持ち出しを強く抑制できると考えるが、見解をうかがう。
A:
画像や動画で学習の様子を記録することは重要であり、現在は公用で一括管理をしているデジタルカメラでの撮影をするなど児童生徒に不安を与えないように配慮をしているが、全国では公用デジタルカメラで盗撮をしていたという報道もあり、管理の一層の徹底に努めたい。
ご提案の公用スマートフォンの貸与については、教員の利便性の向上は期待されるものの、その管理者(副校長)の業務の増加が危惧される。
よって、今後機能更新される全教員に貸与している端末の活用状況を踏まえ、スマートフォンの貸与については、その有効な活用方法も含めて検討する。
(感想)
犯罪行為を発生させないためには、その根源を断つ必要があります。私が個別にヒアリングをさせていただいた全ての学校長から、公用スマートフォンの貸与の要望がありました。
校内で何か不祥事が発生した場合には、まずは学校長がその管理責任を問われますが、学校長は管理下の全ての教職員の私生活や趣味・嗜好までを把握はできません。
学校長の精神的負担軽減のためにも、引き続き働きかけを実施してまいります。
【小学5年生の林間・臨海学校への公費負担を】
(答弁者:教育委員会事務局次長)
Q:
小学6年生で実施されている日光移動教室や、小学5年生の一部の林間学校で利用されている江東区立日光高原学園近郊でも、近年は熊の出現が確認されている。
そこで、熊に遭遇した際の教員や児童に対する指導内容と、予防的処置についてうかがう。
A:
日光市やビジターセンターなどから現地周辺情報を収集し、適時、利用する学校に注意喚起を実施している。
また、ハイキングなどに携行するための“熊鈴”を現地に配備したり、状況に応じてハイキングコースの変更や、早朝・夜間の活動を屋内で行うなど、安全に努めている。
Q:
5年生の全校で実施されている林間・臨海学校は教育課程外の位置づけであり、公費負担は無く、各校が主体的に実施をしている。
また、出欠は各ご家庭の判断に委ねており、教育委員会としては参加状況についても関知をしていないが、全てを学校任せの現状が健全であるとはとても思えない。
よって、経済的理由やいじめで参加できない児童がいる可能性も排除できないため、当該行事は教育課程内へ移管をして全額公費負担とし、教育委員会が主体的に関わり、今後も永続的に実施するべきである。
加えて、教育課程内に移管することで夏季休業中から外すこととなるため、教員の働き方改革にも直結すると考えるが、見解をうかがう。
A:
本行事は企画、宿泊先や移動手段の確保、費用の徴収など一連の事務を学校が担っており、相応の負担をかけていることは認識している。
また、夏季休業中の実施による教員の負担感のみならず、近年の猛暑による夏季の実施についても課題となってきている。
そこで、教育課程内への移管について各校に確認をすると共に、公費負担についても、学校と連携しながら必要な見直しを進める。
(感想)
学校は教育の場のみではなく、保護者対応や地域との連携など、本来教員が担うべき以外の多種多様な業務にも忙殺されています。
教育的効果が極めて高い伝統的行事である林間・臨海学校について、学校に全てを委ねている現状はあまりにも無責任であり、早急に改善するべきと考えます。